AI時代にリベラルアーツ?
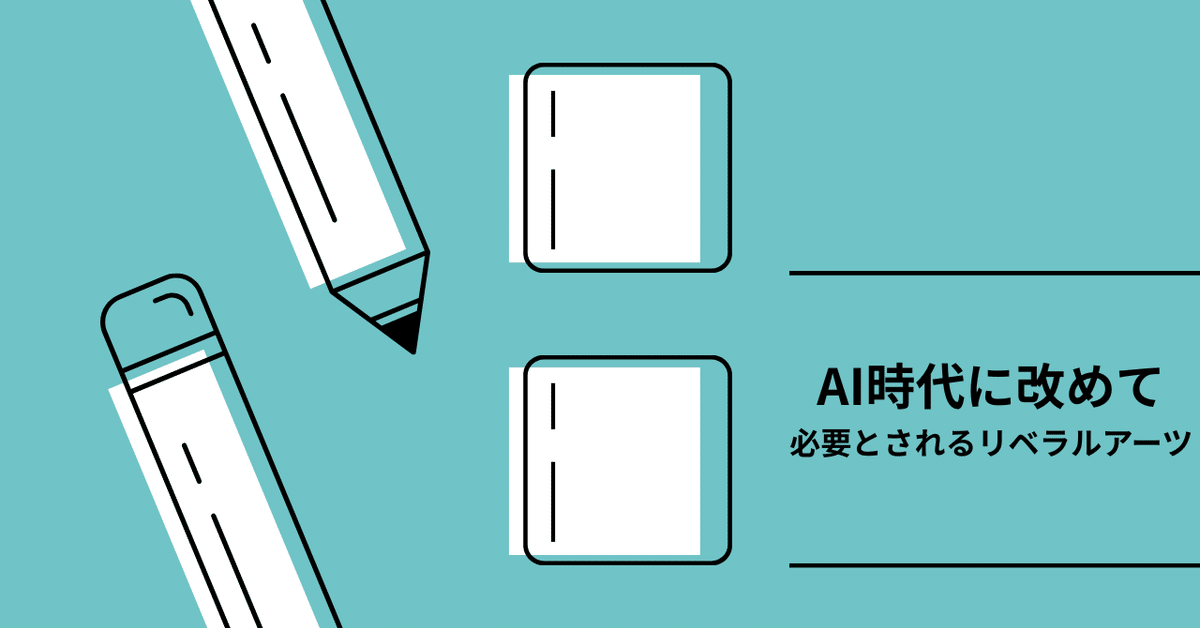
「問いを立てる」力が大事。哲学・歴史・文学
最近よく耳にする「AI時代にこそリベラルアーツが再評価されている」という話に、自分のルーツを重ねてみました。
AIが人間の「判断」や「思考」を模倣することが増えるいま、本当に大事なのは「そもそも、これはどういう意味なのか?」と問い続ける力だと感じています。
中学から大学まで、「生活即教育」の環境で哲学・歴史・英語・数学・中国語など多領域に触れながら自分の問いを磨いてきました。そこには、偏差値評価では測れない“自分なりの戦略”があった気がします。
ソフトウェアエンジニア・コンサル・CS責任者として歩んできた今は、技術やビジネス、語学が、自分型の武器になっています。T型人材ではなく、“意味で組み合わせた自分型”みたいなものが、AIと共生できる強みかもしれないなと思っています。
問いの質や意味を大切にした経験を、言葉を通じて誰かに届けられたら嬉しい。その想いを込めて書きました。
記事概要
-
AI時代、「問いを立てる力=リベラルアーツの価値」が再評価されている視点を提示
-
自分のルーツとして、中高→大学時代のリベラルアーツ教育があった背景を紹介
-
知識や技能では測れない“問いを継続する力”が、生きる戦略として効く話
-
技術・ビジネス・言語の交差で築いた「自分型」キャリアについて振り返り
-
“T型”じゃなく、“意味と問い“を中心に据えた「問いづくり型」の生き方提案
